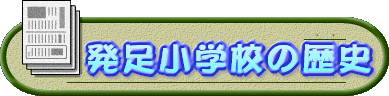
平成元年〜現在
昭和63年度以降、児童数の減少が著しく、特に、平成元年度には児童数が20名を割り、3学級4定員という厳しい状況となった。このため、数年継続してきた「ふるさと自然学習」で取り組んでいる素材の縮小整理を余儀なくされるに至った。
しかし、「さけの飼育」学習は、本校の教育活動の中心としての役割はもとより、厚田村の特色として位置づけられるまでになり、従来の規模で実践を継続することにした。そのために、元年度に水源地及び送水管の補修をしたが、部分的補修ではどうしょうもなく、平成2年度からは、飼育用水槽やヒ−タ−、エヤポンプ等施設設備の更新をし、水道水での飼育に切り替えることにした。
更に、平成2年度には、待望久しかったグランドが暗渠入りで全面改修された。平成3年11月には、厚教研学校研究課題発表会が本校で行われ「ふるさと自然学習」に関した授業実践を公開し、大好評を得た。
平成4年11月には、屋体暖房器が、12月には雪囲い施設が設置された。
平成5年9月には、開校90周年記念式典を実施し、また、10月には石狩管内複式教育研究会の会場校として、極小規模校における研究実践と一人一人の子どもたちの生き生きとした活動を公開する。
平成8年11月には、厚教研学校課題研究発表会が本校を会場に開催され、9名の児童が理科・生活科の授業、一輪車・自然の楽器等で生き生きと発表した。
平成9年度は、本校の「ふるさと自然学習」について、総合的に見直しを図るために、「総合カリキュラム」を作成した。
平成10年度は、「総合カリキュラム」により実践・検証し、ふるさとの自然を生かした教育のあり方について追求する。
平成11年度は、児童の思いや願いを前面に出すことを全ての教育活動の中心に据えてふるさとの自然学習の中から地域のさまざまなことがらを児童主体で「発見」したり「体験」したりする「発足タイム」の時間を設定した。
また、新指導要領に基づく、教育課程の編成、実施に向けて、本校児童の力を分析し他との交流を基盤にした 社会性の育成を重点とし、教育計画を作成、実践した。
社会性の育成を重点とし、教育計画を作成、実践した。
平成12年度は、平成14年度から全面実施される「総合的な学習の時間」の先行実践に取り組み、発足小学校の新教育課程の全体構想を明確にした。
新教育課程の全体構想では、「ふるさと自然学習」を「総合的な学習の時間」に再編成して結合し、平成
11年度に創設した「発足タイム」は、「総合的な学習の時間」に発展解消した。
平成12年8月には、全国小学生長雑巾がけ選手権に「全道五つの小規模校連合チーム」の一員として
出場、自己ベストの記録を出し、大いに健闘した。
7月の美瑛における合宿練習並びに東京大会の出場を通して、発足小学校の子供たちは、全道、全国
の子供たちとの友情を深める貴重な体験をした。
平成13年度は、「総合的な学習の時間」において、子供達や先生方のユニークなアイディアや豊かな発想に基づく実践が多くなされ、発足小学校の総合学習の」理論と実践が深められ、石狩管内教育実践研究報告書にその内容が掲載された.
平成13年11月15日には、堀達也北海道知事の学校訪問があり、子供達の鮭学習の様子や鮭太鼓の演奏を参観していただいた.昼食時には、堀達也北海道知事と子供達が給食を一緒にいただき、親しくお話し合いを行った.
平成13年度のはじめより、発足小学校の閉校問題についてPTA、自治会と話し合いを行ってきたが、平成13年11月22日の発足自治会臨時総会、11月28日のPTA臨時総会において結論を得た.
発足小学校は、平成15年3月末をもって閉校し、100年の歴史に幕を閉じることになった。

